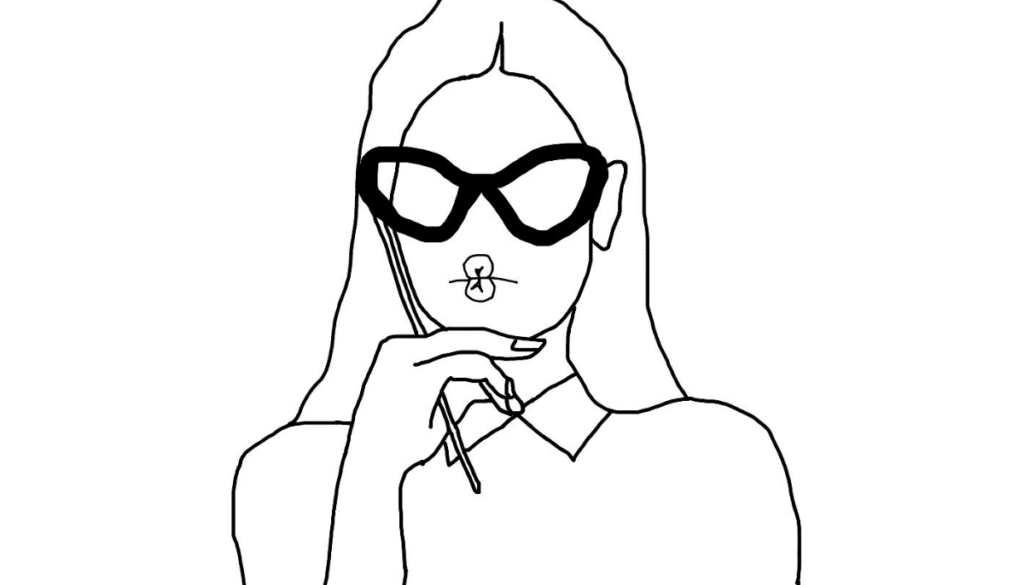市立豊中病院編〜市民福祉常任委員会【2023年度決算】
患者相談窓口における性被害相談
山田:大阪唯一の性暴力救援センターが経済的事情や医師不足により医療体制維持が限界にあり、府内に10箇所ある大阪SACHICO協力病院を受診する性被害者の数が増えているそうです。そこで、市立豊中病院に伺います。病院の患者相談窓口における、性被害に関する相談件数の実績について教えてください。
豊中市:市立豊中病院の患者相談窓口における性被害に関する相談については、令和5年度においては相談件数はゼロでした。
患者相談窓口において性被害に関する相談があった場合については、相談内容に応じた、院内での担当部局や院外の関係機関等についての対応手順を定めているところです。
山田:2023年度、患者相談窓口において、性被害に関する相談はなかったとのことでした。
意見要望です。豊中市が推奨する性被害にあった時の連絡先の一つが大阪SACHICOです。冒頭でも申しましたが、大阪SACHICOは現在、経済的困難や医師不足により運営の危機に瀕しています。9月14日付の毎日新聞の記事によると、大阪SACHICOへの電話相談は2022年度4231件、2023年度に3561件寄せられ、来所者数も2022年度は406件、2023年度は121件あったが、今年度は1人も診療できていないとのことです。
大阪SACHICOのこういった診療不可である現状は、当然豊中市内の性被害者にも影響があるわけで、性被害がおこった時の相談窓口を大阪SACHICOに頼っている豊中市としても何か対策を打つなり新しい方針を立ち上げることが必要と考えますが、まずは市立豊中病院でも、この事態を受けて、急な性被害の相談や受診に十分対応できるように、今まで以上に備えておく必要があると考えます。ご検討のほどよろしくお願いいたします。
がん診療連携拠点病院
山田:地域がん診療連携拠点病院とはどのようなものか。教えてください。
豊中病院:国のがん対策は、がん対策基本法及び同法に基づく「がん対策推進基本計画」により総合的・計画的に進められています。これらに基づき地域がん診療連携拠点病院は、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん医療の均てん化を目指し、厚生労働省がその整備を進めてきました。大阪府内では本年 4 月現在、都道府県内のがん治療の推進を担う都道府県がん診療連携拠点病院 1 施設、各地域の拠点となる地域がん診療連携拠点病院が当院を含め 16 施設が指定されています。
山田:地域がん診療連携拠点病院の指定については、具体的にはどの様
な要件があるのか。また、地域がん診療連携拠点病院であることの
メリット・及び加算について教えてください。
豊中病院:指定要件の具体的な内容は、「診療体制」「診療実績」「人材育成等」「相談体制及び情報の収集・提供体制」「臨床研究及び調査研究」「医療の質改善・安全管理」など 300 近くの項目について報告し、審査を受けることになります。次に地域がん診療連携拠点病院であることのメリットでございますが、今申し上げました要件を満たす、質の高いがん治療の水準を維持することで、地域医療全体のがん治療のレベルの底上げにつながり、市民にとっても身近に高度ながん治療が受けられるメリットがあると考えています。また、高度ながん治療を提供する人材や設備などの機能を有することから、新たな知識やスキルを身につけたい医師などの人材確保について優位になると考えています。最後に診療報酬の加算については、紹介により入院したがん患者の入院初日に5000円が、がん拠点病院加算として算定できます。令和 5 年度の実績は、977 件で 4,885,000 円となっております。
山田:病院のメリットとしては、どちらかというと病院のブランド力や高度なスキルを持つ医師の確保といったところでしょうか。地域がん診療連携拠点病院であることは大きなメリットだと考えます。
3問目です。令和5年度の呼吸器外科の医師の配置人数を教えてください。また今年度については、呼吸器外科医が不在のようですが、肺がんや気胸など呼吸器外科の疾患に対して、どのように対応しているか、お聞かせください。
豊中病院:令和5年度、当院に在籍していた呼吸器外科常勤医師の人数は2名でした。ご指摘の点につきましては、年度末の医師の退職により常勤医師は不在となりましたが、当院は大阪大学医学部附属病院の医局と連携しながら、地域医療体制の維持に努めており、現在、呼吸器外科の外来診療は大阪大学医学部附属病院より定期的に医師の派遣を受けながら、診療体制を維持しております。また手術が必要な場合は、大阪大学医学部附属病院や大阪刀根山医療センターと連携して対応しております。
山田:医師の確保体制と確保の見通しはどのようになっていますか。お聞かせください。
豊中病院:当院では、大阪大学医学部附属病院の医局と連携しながら、各診療科の医師を確保しております。次年度以降の呼吸器外科医の配置についても調整を行なっており、次年度当初時点での常勤医の配置を見込んでいるところです。
山田:医師の派遣は、大学医学部が人事権を握っており、特定の大学医学部(豊中の場合は大阪大学)以外に派遣要請しにくいことは聞いてはいます。それでも、敢えて、他の大学医学部への派遣要請やフリーランス医師への募集、ヘッドハンティングということは考えなかったのか、と言う疑問が残りますがまたの機会に改めて伺うことにします。
5 問目です。臨床研修医の指導について、市立豊中病院は全国的にも定評があり、今年も多くの医学生が卒後研修先の病院として市立豊中病院を志望していると聞きます。そこで、医療の質を担保するために、2023年度はどのような体制のもと研修が行われたのか、お答えください。
豊中病院:当院は臨床研修指定病院として、初期臨床研修医の教育・指導を行うとともに、教育活動を通じて大学との連携強化に努めています。令和 5 年度についても、指導医講習を修了した指導医やその他の上級医、看護師、薬剤師など多職種の指導者が各診療科ローテーションや講義、実習を通じて、初期研修医の指導を行うとともに、豊中市医師会の先生方に協力いただき、豊中市保健所とも連携しながら、地域医療の研修にも積極的に取り組みました。また初期研修医からの評価を指導者にフィードバックすることで、指導者側の資質向上に役立てました。指導者は連絡会を定期的に開催し、研修の進捗状況や研修プログラム、改善すべき課題を確認し、より充実した研修実施に繋げました。初期研修終了後の専門医育成(後期研修)については、大阪大学や地域の医療機関と連携し、各診療科の専門研修プログラムに沿って、各診療科単位で専門研修を実施しています。
山田:意見要望です。市立豊中病院で研修した医師がその後も市立豊中病院で勤務を続けられるように、積極的にキャリアアップを促し、必要に応じてライフワークバランス調整ができるような工夫や改善なども常に必要かと思います。地域がん診療連携拠点病院の「診療体制」「診療実績」「人材育成等」「医療の質改善・安全管理」といったこれらの指定要件を満たすためにも、せっかく市のリソースをさいて育てた専門職が簡単に離職しないような工夫も要望しておきます。この質問を終わります。