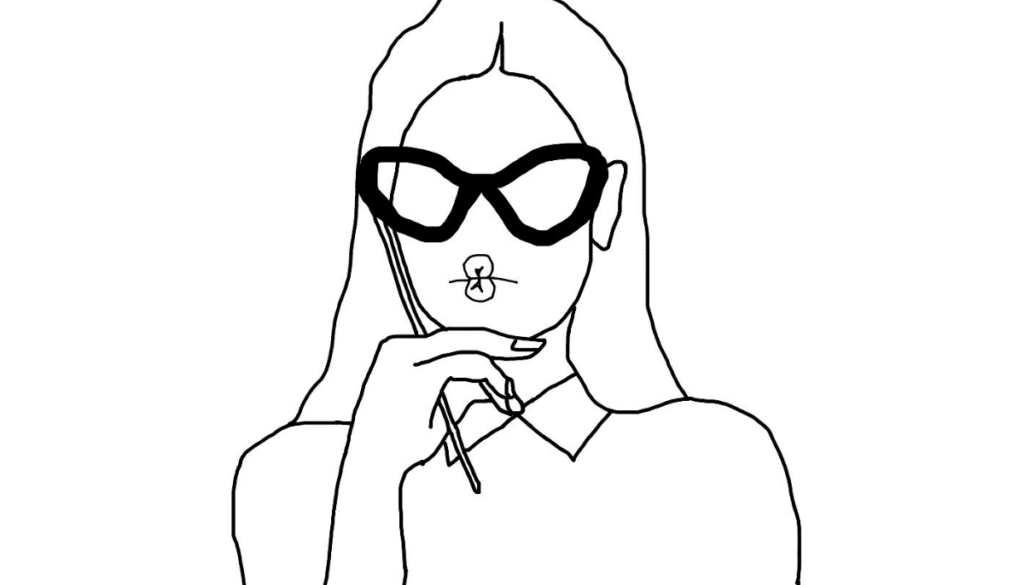福祉部編〜2024年度市民福祉常任委員会【決算委員会】
移動支援事業
山田:移動支援は障害者が地域で人間らしく生きていくためにとても大事な事業と考えます。過去3年の移動支援の、のべ利用者数と事業所数の推移、豊中市の利用時間の支給量基準と同規模他市(吹田、高槻、尼崎など)ではどうなのか教えてください。
豊中市:移動支援の利用者数につきましては、令和3年度が延べ11,543人、令和4年度が延べ12,137人、令和5年度が延べ13,075人でございます。本市指定の事業所数につきましては、令和3年度が287事業所、令和4年度が299事業所、令和5年度が313事業所でございます。また、本市の1月あたりの支給量基準は、障害者が40時間、障害児が通学支援を除き最大32時間となっております。なお、本市の支給量基準にあたる時間数につきましては、同規模近隣市では吹田市が障害者は40時間・障害児は12時間、高槻市が障害者は40時間・障害児は30時間、尼崎市が障害者・障害児ともに50時間となっております。
山田:移動支援が非常に需要の高い事業であることがわかりました。
従事者資格の要件について教えてください。また資格研修を受ける際の補助があればより多くの方が資格対象者となり人手不足の解消の対策になるかと思うのですが、市の見解をお答えください。
豊中市:移動支援に従事するためには、介護職員初任者研修等の修了もしくは介護福祉士等の資格が必要となります。なお、より多くの従事者確保の観点から、様々な補助があれば有効であると考えており、本市では令和5年度から「豊中市介護・障害サービス分野への資格取得・就職応援事業」により、介護職員初任者研修に係る費用の補助を実施しております。
山田:令和5年度より「豊中市介護・障害サービス分野への資格取得・就職応援事業」により、介護職員初任者研修に係る費用の補助を実施しておられるとのこと、大いに評価いたします。今年度の移動支援の従事者増加を大いに期待するところです。
報酬の単価をあげることはお考えですか?また、豊中市の単価と、近隣市との比較を教えてください。重度障害の市民の方から日曜日が使えない。一番外出をしたいのが日曜日なのに。ということで相談を受けました。また、例えば市独自で日曜日に報酬の上乗せなど、日曜日が使いにくい状況への対策をお考えですか?市の見解をお答えください。
豊中市:身体介護ありの場合のサービス提供開始30分当たりの報酬単価で申し上げ
ますと、本市は2,440円、先程比較いたしました同規模近隣市では、吹田市が
2,440円、高槻市が2,350円、尼崎市が2,165円となっております。
なお、利用者からの日曜日のサービス利用に関するご意見について特には
聞き及んではおりませんが、まずは、個々のケースに丁寧に寄り添い円滑な
サービス提供に繋がるよう、引き続き、7圏域の相談支援センターとも連携を
密に図り取り組んでまいります。
山田:意見要望です。利用当事者の声、「日曜日は重要が多く、人員不足のため、外出できない」との訴えは切実だと思われますので、ぜひとも当事者に寄り添った受け止めとサービス提供を改めてお願いします。2022年に国連から日本に出された勧告では、障害児を含む障害者の施設収容を廃止するため、「予算配分を障害者の入所施設から、障害者が地域社会で他の人と対等に自立して生活するための手配と支援に振り向けることによって、迅速な措置をとること」「すべての地域において障害者の自由な身の回りの移動を確保すること。」なども含まれています。障害者施策を進めるためにも、以上申し述べた点の迅速な取り組みを強くお願いし、質問をおわります。
訪問入浴サービス事業
山田:本事業は、「家族のみでは入浴困難な重度身体障害者に対し、必要な設備
等を提供し入浴の介助を行う」ものと聞いていますが、過去3年間の延べ
利用者と実利用者数、市の指定事業所数の推移について教えてください。
豊中市:延べ利用者数につきましては、令和3年度が延べ246人、令和4年度が延べ253人、令和5年度が延べ215人でございます。実利用者数につきましては、令和3年度が23人、令和4年度が22人、令和5年度が22人でございます。指定事業所数につきましては、令和3年度から令和5年度までいずれも7事業所でございます。
山田:お答えでは、利用される障害者が、平均、年間10回ほどしか入浴できていないということを示しているのでしょうか。訪問入浴サービスの利用回数は月10回まで、とされていますが、実態は、平均、年10回です。
訪問入浴サービスがない日に重度身体障害者は入浴しないのでしょうか?
他に入浴介助を受ける機会があるのであればどんなものがあるのか、教え
てください。
豊中市:生活介護等の通所施設における入浴や、入浴ではありませんが、家族・ヘルパーによる清拭が考えられます。
山田:通所施設には入浴設備がないところもあるので、また、家族やヘルパーによる清拭(せいしき)もそうですが、これについては個人差があると言うことがわかりました。
市内の重度身体障害者が満足に入浴、または清拭(せいしき)できているかどうかは生存権にも関わります。市で把握はありますか?ない場合、まずは把握のために、アンケートを実施してはいかがでしょうか?市の見解をお聞かせください。
豊中市:令和6年度から令和11年度を計画期間とする第六次障害者長期計画策定の過程において、障害福祉分野に係る市民アンケート調査を実施する中で、入浴サービス利用を調査項目としております。調査結果を踏まえつつ、訪問入浴サービスにつきましては、障害福祉サービス全体を考慮して利用回数を定めております。
山田:意見・要望です。2024年度から2029年度を計画期間とする第六次障害者長期計画策定の過程において、障害福祉分野に係る市民アンケート調査の結果を拝見しましたが、入浴サービス事業に不満がある方が35%もいらっしゃいました。不満内容の調査では、利用したい日や時間に利用できないことや、利用回数や時間に制限があることが一番多いという結果でした。このアンケートでは答えた方がどの事業やサービスを利用しているか、などが明確ではないので、さらに詳しいアンケートを実施していただくことを要望します。重ねて申し上げますが、入浴は生存権に関わります。なにとぞ、よろしくお願いいたします。この質問は以上とします。
個別避難計画
山田:昨年度は、今年度からの計画作成に向け、関係団体等と意見交換会
を開催されたとお聞きしています。意見交換会は、どのような方と何
回実施されたか、お答えください。
豊中市:昨年度は、今年度からの本格的な計画作成のために、ケアマネジャー等の福祉専門職や民生委員等の地域支援者、障害者等の当事者団体との意見交換会を17回、開催しました。
山田:昨年度は、一昨年度と同様、モデル事業を実施されたとお聞きしま
したが、実施内容について、お聞かせください。
豊中市:一昨年度に実施しましたモデル事業は、地震を想定したものでしたが、昨年度は昨今多発する風水害を想定したモデル事業を実施しました。内容としましては、個別避難計画のデジタル化を想定したスマートフォンやタブレットを活用した安否確認訓練の実施に加え、風水害にも対応した新たな計画様式に福祉専門職が記載頂き、実際の避難支援へのご意見をいただきました。
山田:誰でも、すぐに避難できるように、最寄りの避難所を福祉避難所と
しても利用できるようにしたらどうかと考えますが、この点について
の見解をお聞かせください。
豊中市:現在、優先対象者の個別避難計画を作成しており、計画を作成する中で、避難先の調整も実施する予定にしております。また、昨年度のモデル事業の検証結果から、日頃からつながりのあるサービス利用事業所への避難を希望される方が多かったため、まずは、対象者ご本人が希望される事業所を避難先にできないか調整することとしております。優先対象者は、要介護4と5、または、身体障害者1級の単身者でその他の条件を満たされる方であり、移送や避難先において、福祉サービスも必要になることが想定されるため、計画作成と合わせて、特別養護老人ホームを運営している事業者等に避難先の受け入れと移送の協力依頼を進めております。
山田:普段通い慣れた事業所への避難を希望される方が多かったとのことです。
意見要望です。使いなれた事業所が過ごしやすいことは、事業所が高齢者、障害者に合わせたバリアフリー構造であることを考えると当然なのですが、事業所に被害があった場合や、たどり着けないことを想定すると、近くの、最寄りの避難所への避難も当然、可能性は高いと思われます。したがって、流動食や食べやすい食事、災害用トイレ、ベッド、紙おむつ、清拭(せいしき)タオル、清浄綿などの備品等、要介護4・5や身体障害者1級の方が避難所で快適に過ごせることを想定した備蓄品を保管しておくことが不可欠です。危機管理課と連携するなどして、大小あらゆる被害状況を想定しての個別避難計画を立てていただきますよう切に要望し、この質問を終わります。
扶助費支給事業決算額
山田:本市の生活保護受給者数の過去5年の推移を教えてください。本市の同規模近隣市の同じく過去5年の生活保護受給者数の推移についても教えてください。
豊中市:まず本市の生活保護受給者数の推移ですが、各年度の3月末時点の数値で令和元年度9,853人、令和2年度 9,709人 、令和3年度9,497人、 令和4年度9,539人、 令和5年度9,560人です。同規模近隣市の生活保護受給者数の推移ですが、同じく各年度の3月末時点の数値で、吹田市では令和元年度5,601人、令和2年度 5,687人、 令和3年度5,608人、 令和4年度5,638人、 令和5年度5,692人、高槻市では令和元年 5,838人、 令和2年度5,802人、 令和3年度5,771人、 令和4年度5,660人、 令和5年度5,663人、尼崎市では、 17,712人、 令和2年度17,400人、 令和3年度17,193人、 令和4年度16,986人 令和5年度16,794人です。
山田:2023年度に実施した厚労省の生活基礎調査によると生活が苦しい国民が6割との結果ですが、豊中市でも近隣他市でも生活保護受給者数が増加傾向にはないことがわかりました。
本市の過去3年の申請数と開始数の推移を教えてください。
豊中市:令和3年度の申請数は716件、開始数は686件、令和4年度の申請数は895件、開始数は855件、令和5年度申請数は893件、開始数は860件です。
山田:開始数について、2022年度から2023年度は微増であるものの生活保護を開始する方が毎年増えていて、毎年申請者全体のうち約5パーセントの方が申請したが開始にならなかったことがわかりました。
扶養照会についてどう取り扱っているのか、実施状況について教えてください。2023年度中に開始した世帯にかかる扶養能力調査実施件数も合わせてお願いします。
豊中市:扶養義務者の扶養は、保護に優先して行われるものと定められており、保護の要件とは異なる位置付けのものと規定されております。本市においても国の通知に従い、よう保護者等から聴き取りを行い、扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者等の場合、一定期間音信不通であるなど交流が断絶している場合、また扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかによう保護者の自立を阻害することになると認められる場合など、扶養義務のりこうが期待できないと判断された場合は、基本的に扶養義務者への直接の照会を行わない取扱としております。なお、扶養能力照会を行う場合については、被保護者にあらかじめお伝えした上で実施しております。令和5年度中に開始した世帯にかかる扶養能力調査実施件数は、1,348件です。
山田:意見要望です。豊中市が2023年度に行った扶養能力調査実施件数は1,348件とのことでした。同年の被保護世帯が7,569世帯なので照会率は約18パーセントということです。2021年に厚生労働省は扶養照会の運用を改善しましたが、一度は扶養照会をする前提で話が進むことは変わりません。答弁の中にもありましたが、話の中で扶養義務の履行が期待できないと判断された場合に扶養義務者への直接照会を行わないと言うことでした。以前、市民の生活保護の申請に付き添いました。保護に先立って扶養照会の手続きの説明がなされ、手続きが粛々と進められようとしました。申請者は心身ともに非常に弱っていらっしゃったので、1人で申請ができる状態ではないと言うことで私のもとへこられたわけです。ですので私が代わりに「親族との関係性が悪化する恐れがあるので扶養照会をやらないように」とお願いをし、その上で担当者は「検討をする」とだけ、いいました。結局最後まで「扶養照会はしない」という意思表示が、ありませんでした。結果的に扶養照会はありませんでしたが、私が同行していなかったら、当該申請者は生活保護の申請を諦めていたのでは、とさえ思いました。生活保護が受けられなかったら死ぬしかないと思っていた、とも私に対してお話しされていました。日本では生活保護はとてもネガティブなイメージがあります。できれば受けたくない、恥だ、受けるくらいなら死んだ方がましだ、そういった誤った価値観を引き起こす偏見や「レッテル」が社会に蔓延しています。その証拠に日本の補足率は先進国の中で非常に低い数値に止まっています。捕捉率は、生活保護制度の対象となる人の中で実際に利用している人の割合です。日本の補足率はおよそ2割だといわれています。ヨーロッパでは8割を超える水準です。全国74自治体の扶養照会の運用実績をもとにした朝日新聞が行った調査報道により、「千人への扶養照会で、仕送りにつながったのは7人に満たない」ことや、照会率の自治体間格差が広がっていることが明らかになっています。「困窮者支援団体などは「扶養照会は水際対策」と問題視しています。(東京弁護士会が紹介していましたが)一般社団法人「つくろい東京ファンド」が実施したアンケート調査で、生活保護を利用しない理由として「家族に知られるのが嫌」が34.4%と最も多いことがわかっています。福祉事務所は、窓口で申請手続きを扶養照会を前提として進めるのではなく、申請者にまずは扶養照会の可否を伺うべきです。申請時の対応の改善を検討いただくことを強く要望します。また、自動車保有についても生活保護申請をためらう一員と言われていますが、「生活保護か自動車か」と迫られる現場がまだまだあるそうですが、少なくとも、①公共交通機関の利用が著しく困難な場合の通勤や通院等のための保有が認められる、②通勤のための利用には保育園への送迎も認められます。③保護を受ける際に仕事に就いていない場合でも、1年(場合によってはそれ以上)にわたって車両の処分を保留してもらうことができる、などの情報は窓口で申請者にも正しく伝えていただくことを要望し、私の質問を終わります。
訪問介護について
山田:まずは訪問介護事業のニーズについて、市の認識をお聞かせください。
豊中市:昨年度、第 9 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定における介護給付費の推計では、令和 8 年度 介護給付費 87 億4千4百万円、回数249,867 回、利用人数 6,591 人、毎年3~4%の伸びを見込んでおり、居宅サービスにおいてニーズの高いサービスであると認識しております。
山田:過去3年間の訪問介護の市内事業所数、新規指定数、廃止数についてお聞かせください。
豊中市:指定申請中も含み4月1日時点の事業所数は、令和3年度 181か所、令和4年度 189か所、令和5年度 193か所でございます。各年度の新規指定数は、令和3年度 7か所、令和4年度 15か所、令和5年度 12か所でございます。各年度の廃止数は、令和3年度 7か所、令和4年度 14か所、令和5年度 10か所でございます。
山田:訪問介護事業所数は少しずつ増えてはいますが、一定数の事業所の廃止があることも同時にわかりました。
2024年度の報酬改定では、訪問介護の基本報酬が下がり、訪問介護の現場からは国へ対して悲痛な意見があがっていますが、市では、これまでどのような状況でしたか、今後の動きも併せて教えてください。
豊中市: 市では、事業所から廃止届を受ける際に可能な範囲で理由をおたずねしますが、主な理由としては、高齢になったから、後継者がいないから、利用者が確保できないからと聞いており、報酬改定時には、新たな加算等の事務手続きの負担についてご意見をいただいているところです。訪問介護における基本報酬改定の経営的な影響は、国が実施する効果検証の調査研究とともに、市においても事業所数や介護給付費の動向、事業所からの問い合わせや相談等を踏まえて検証してまいりたいと考えております。
山田:人材確保についても厳しい状況が続いています。市のこれまでの介護保険事業所に対する支援と今後の取組みについてお聞かせください。
豊中市:人材確保については、研修事業をはじめ、令和5年度から介護・障害福祉サービス分野の資格取得や就労支援を目的とした助成事業を実施するとともに、介護保険事業所の団体が主体となって取り組む人材確保等を助成する事業の制度設計に取り組みました。現在、公募により決定した団体の事業展開に対し、相談助言等の伴走的支援に取り組んでいるところでございます。
山田:かねてから、今年6月から始まった報酬改定に伴った訪問介護の報酬引き下げについての問題点を指摘してきました。答弁の中でも市に早速事務手続きの負担についての意見が寄せられているとのことでした。他にも職種間・事業所間の賃金バランスの問題も指摘されていますので、訪問介護報酬引き下げの事業者への影響を今後も注視していただくよう要望してこの質問を終わります。
介護保険料について
山田:2023年度策定の第 9 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、計画期間中における介護保険料の月額基準額は 6,998 円と、631円の値上げとなりました。介護保険料の開始当初と比較すると2.2倍になっていて、高齢者の負担額は無茶なレベルです。どのような内容を踏まえて算出されるのか教えてください。
豊中市:3 年間の計画期間中における 65 歳以上の第 1 号被保険者数の推移や施設系・居住系サービスの必要量をもとに、標準給付見込額等を推計し算出
するものでございます。
山田:推計では、第 9 期の月額基準額は当初 7,424 円でしたが、保険料額を抑制するために介護保険準備基金から約 16.6 億円を取り崩し、最終 426 円マイナスの 6,998 円とのことでした。この介護保険準備基金は第 1 号被保険者の保険料の余剰分を毎年積立て次期計画の保険料上昇の抑制に活用するものですが、なぜ、制度当初に国から交付を受けた円滑導入特例交付金3.6 億円を積み残すのか、理由をお聞かせください。
豊中市:この円滑導入特例交付金は、介護保険制度の円滑な導入と設置する基金の造成事業に対して交付されたものでございます。本市は、その制度趣旨や審議会の答申を踏まえ、赤字等の財政危機が生じた場合に備えて積み残し、介護保険財政の安定的な運営に生かしているものでございます。
山田:意見要望です。介護保険料は開始当初と比較すると、2.2倍に上昇しています。2040年推計では9,879円です。介護保険の値上げは持続可能ではないと言わざるをえません。政府は国の責任をごまかし、持続可能な制度の姿を示すこともできていません。「介護の社会化」といいながら、低水準の国庫負担を維持しています。誰もが必要となる高齢化による医療や介護、生活保障については、逆進性の強い(所得の低い人の負担割合が大きい)保険制度や消費税を財源とするのではなく、当面は国債発行により危機を乗り越えながら、長期的には累進性の高い税制度により持続的な制度への抜本改革が必要と言えます。しかし、国が打ち出す政策は、高齢化にともなう支出増加に対し、「国債発行により将来世代に負担が先送り」「現役世代の負担が年々重くなる」などと、高齢者世代と現役世代、将来世代を対立させ、高齢者に負担を求める議論に終始し、「高齢化による増加分におさめる」方針をとり、介護への公的支出増大を抑制することばかりです。豊中市は国の責任逃れの介護保険制度政策に強く抗議するべきだと意見してこの質疑を終わります。
紙おむつ給付事業
山田:紙おむつ給付事業は地域支援事業における任意事業の「家族介護支援事業」のうち介護用品の支給事業のひとつで、税と1号保険料を財源としており、国が(38.5%)、大阪府が(19.25%)、市が(19.25%)、1号被保険者保険料にて(23%)負担する事業です。まずは事業内容と対象者の要件を教えてください。加えて過去3年間の利用者数の推移を教えてください。
豊中市:本事業は要介護3〜5で本人及び同居する人全員が市民税非課税世帯である人を給付対象としています。実績につきましては、令和3年度から令和5年度まで順に、要介護3が1,543件、1,518件 1,666件、要介護4・5が2,751件 2,798件 2,867件でした。
山田:実績が、2021年度から2023年度の間でトータルで239件増加しており、需要が高いことがわかりました。
「生活が苦しいのは非課税世帯だけではない。対象者を広げてほしい」と市民の方から相談がありました。最新の厚労省の生活基礎調査では、生活が苦しいと感じる世帯は約6割となっています。豊中市の生活実態は、19万世帯中11万世帯の所得収入が300万円未満です。課税の方へ対象者を広げるべきではないですか?
豊中市:本事業は介護保険事業のうち、地域支援事業として実施しているものです。国の地域支援事業交付金の対象は、「平成26年に介護用品支給事業を実施している市長村のうち、令和5年度に介護用品支給事業を実施している市町村であって、第9期介護保険事業計画期間において市町村特別給付及び保健福祉事業等への移行を含めた計画的な事業の廃止・縮小に向けた取組を行う市町村」とされています。課税の方へ対象を広げることにつきましては、介護保険特別会計や一般会計への影響を精査し、慎重に取り組むべきものと考えております。
山田:意見要望です。国が2023年12月に市町村宛で出した「地域支援事業のうち介護用品の支給に係る事業の 第9期介護保険事業計画期間における取扱いについて」によると、国はいずれ、「市町村特別給付」や「保健福祉事業」または市町村独自事業として実施することを、市町村に求めています。すなわち、紙おむつ支給事業の国と都道府県の負担分を、1号被保険者の保険料、あるいは市町村の独自財源に肩代わりさせようと言うことです。国はこれまで高齢化にともなう支出増加に対し、高齢者に負担を求める議論に終始し、社会保障関係費は「高齢化による増加分におさめる」方針により、様々な給付抑制策が取られてきました。紙おむつ支給事業は需要が非常に高い事業です。対象拡大を求める声が市にも届いているとのことです。繰り返し申し上げますが、少子高齢化が進む中、高齢者の負担増や、利用需要の高い介護用品の支給を含む給付抑制は持続可能な対策ではありません。紙おむつ支給事業の継続を引き続き国に求めることを強く要望しこの質問を終わります。