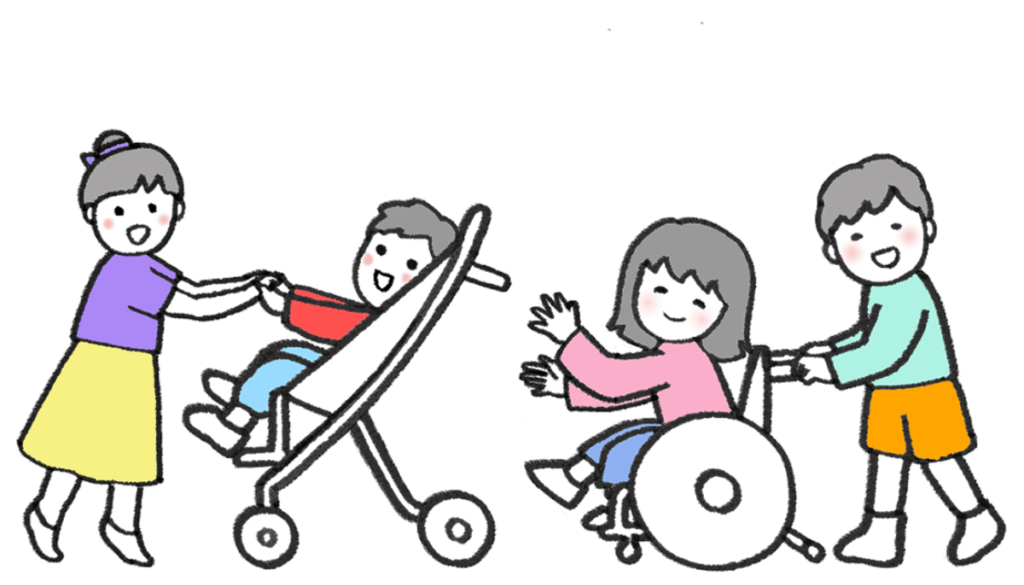2024年12月議会質疑②福祉のまちづくり:議会におけるバリアフリー化の状況
議会におけるバリアフリー化の状況
山田:1991年に全国初の車椅子の女性議員が誕生したことがきっかけとなり豊中市の議場はバリアフリーになっています。当時は非常に先進的なことでした。しかし、傍聴席はいまだにバリアフリーではありません。
どのような経緯で中核市の、インクルーシブ教育が先進的だと言われている自治体の傍聴席がバリアフリーでない事態に至ったのでしょうか。これまでにあった議論はどのようなものだったのでしょうか。また、全ての市民が直接傍聴することは、知る権利の一環として、憲法21条1 項により保障されています。民主主義にとって極めて重要で何人もその権利を保障されるべきですが、市は現状をどう評価しますか。
豊中市:これまでも、議会と情報共有を図りながら、関係部局間でさまざまな検討を重ねてきたが、構造上、エレベーターや車椅子のまま乗っていただける階段の設置は困難で、車椅子から一旦降りて乗降できる椅子型昇降機をH20年度に設置した。車いすのまま傍聴できない状況であることは課題として認識しているが、代わりに職員が可能な範囲で車いすを運搬する、別室のモニターで傍聴していただく等、対応させていただいているところです。
山田:設置型、可搬型共に椅子型昇降機はバリアフリー法の基準を満たしていないことを申し添えておきます。そして職員の方が人力で対応することや別室モニター傍聴、これらは「合理的配慮」とは到底呼べないのではないでしょうか。
2問目です。大阪府下で議場傍聴席がバリアフリーではない自治体は、議場内での傍聴を許可している自治体を除くと数えるほどです。府条例において市庁舎は特別特定建築物にあたり、バリアフリー法への適合義務があると思うのですが、傍聴席に電動車椅子が入れない、または議場に車椅子スペースを設けるなどの合理的配慮を行わないのは問題ではありませんか?また、財源についても伺います。改修改築にあたって財源的に有利な条件があるのでしょうか。例えば起債充当率はどうなっていますか。
豊中市:現状はバリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例に違反しているものではないが、法及び条例の規定をふまえ、今後も検討を進め、適切に対応したいと考えている。起債充当率は、公共施設等適正管理推進事業債を活用する場合は90%です。
山田:起債充当率は90%とのことで、財政に大きくダメージを与えずにやりくりができます。ハードは後年度も使うので、起債にふさわしいものです。豊中の「共に生きる」理念を守る価値ある支出ではないでしょうか?
3問目です。2021〜2023年に何件か議会棟の改修が行われました。どのような必要に応じた改修だったのか、加えて各改修にかかった費用についても教えてください。また、本市議会棟の建て替えをするのであれば、想定される時期についてもお聞かせください。
豊中市:平成 29 年度に第一庁舎及び議会棟の耐震診断を行ったところ、議場の吊り天井の改修工事が必要であるという結果が出たため、安全性の向上を最優先に、令和 3年度から 4 年度にかけて議場の吊り天井の改修工事を実施。工事費は、約 3,700 万円。令和 3 年度には、安全性の向上と施設の長寿命化を図るため、外壁工事や議会棟周りの舗装工事等を実施。工事費は約 1 億 2,500 万円。議会棟は、これら吊り天井の改修工事や維持管理工事を適切に進め、長寿命化を図っており、20年から30年程度は使用できるもの。
山田:1億6,200万円かけて議会棟を改修、維持管理工事が行われ、そしてその結果、これからまだ20〜30年は建て替えの予定はないとのことでした。議会棟の改修時には傍聴席のバリアフリー化についての議論は市側からも市議会側からもでなかったと聞いています。
4問目です。障害者差別解消法では、行政機関は障害のある人への合理的配慮の提供について法的義務を負っています。豊中市の議会傍聴席がバリアフリーでない現状は、問題ではないでしょうか?
また、同法では「行政機関等は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」とあります。市内障害者団体から毎年要望書が出されているはずですが、今まで、議会傍聴のバリアフリー化の要望があったかどうかについてお答えください。
豊中市:障害者団体から、議会傍聴に係るバリアフリーについてご要望をいただいたのは、令和 6年度の1回のみ。車いすのままの傍聴席への昇降には、建物の耐震性能の確保、車いすが旋回するためのスペースの確保など、構造的・物理的な制約があることから、現時点では、車いすの可能な範囲での運搬や、別室のモニター傍聴などで対応させていただいており、現在の状態が直ちに障害者差別解消法に違反するものとは考えていない。
山田:朝日新聞2021年6月15日の記事によると、岐阜県恵那市では約1億9千万円をかけて傍聴席と議場をバリアフリーにしました。障害者団体から議会傍聴のバリアフリー化への要望があり、市は当初、市議会はインターネット中継があり、傍聴は可能だとしていたが、団体側から「自分たちに関係する議案が出た場合は議場で傍聴したい」と主張があり、市は検討を重ね、バリアフリー化を決めたそうです。豊中市の場合、記者席に傍聴席を設けることについて、検討の余地があると考えます。「鉛直型昇降機」と言うものがありまして、これは傍聴席までの階段に現在設置している椅子型の昇降機と違い、バリアフリーと認められている昇降機です。鉛直型昇降機が記者席に設置可能かどうかなど、バリアフリー化の模索検討を進めていただきたいのですが、いかがでしょうか。
豊中市:本市においては、法や府条例に加え、H7年度から、福祉のまちづくり整備要綱を制定し取り組みを進めてきました。庁舎については、構造上の多くの課題に対し工夫しながら、議会傍聴席に椅子型昇降機を設置した他、第一庁舎地下の階段に車椅子のまま乗降できる昇降機を設置するなど、可能な限りの対応をさせていただいています。今後も、多様なご意見をふまえながら、障害者、高齢者のみなさんにご利用いただきやすい施設となるよう、引き続き、取り組んでまいります。バリアフリー化の検討については、引き続き、議会のご意見も踏まえながら対応する。
山田:ありがとうございます。ご答弁によりますと、今、ボールは市議会側にあるということでした。これは当然市側だけの問題ではなく、市議会側の問題でもあります。私も議員になってから1年間、椅子型昇降機がバリアフリー法で認められたものではないということに、気が付かなかったので、そんな自分を恥じているところです。豊中市でも人口4万人規模の恵那市のような取り組みができるはずですが、まずは記者席の改修や鉛直型昇降機の可能性を市議会と市で模索していくべきです。国の法整備に伴い、行政機関には建物適合義務や合理的配慮の義務が課せられています。議会傍聴バリアフリー化是非やりましょう!