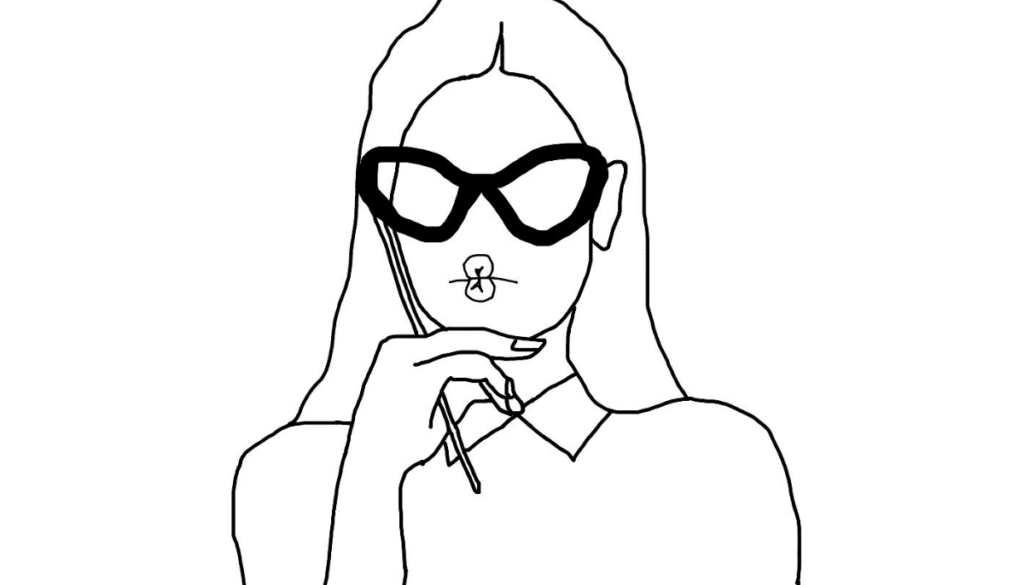市民協働部編〜市民福祉常任委員会【2023年度決算】
とよなか男女共同参画推進事業団の市民との共同企画事業
山田:とよなか男女共同参画推進財団の市民との協働企画事業について伺います。
2023年2月24日付のとよなか男女共同参画推進財団(以後財団とします)に宛てた文書「指定管理業務における助成を伴う事業の再編について」の中で、市は、「女性支援法の制定に伴い困難女性支援のニーズに応じた包括的かつ継続的な「つながり続ける支援」の推進、地域の多様な活動団体に、市の男女共同参画の推進、並びに地域の悩みなどの具体的課題解決に向けてすてっぷとともに取り組んでもらう必要がある。したがって、助成金事業を発展的に解消し、より効果的、効率的に施策を実施できる事業企画として、具体的地域課題の解決に向けたテーマを設定、テーマに沿い市民・団体による提案者とともに共同実施する事業を期待する。」と財団に方向性を示し、その後財団は、すてっぷの事業の中核を担ってきた助成金事業を廃止しました。豊中市は、「市民団体とともに共同実施することを次の事業に期待する」としながらも、すてっぷも中核事業だと認めていた20年の歴史を持つ、助成金事業の廃止決断に至ったプロセスは、登録団体に一言の相談もない、一方的な打ち切りであり、市は、この市民と協働で行う施策を著しく軽視しているとしかとらえようがなく、たいへん乱暴だったと言えます。
財団宛の文書「指定管理業務における助成を伴う事業の再編について」を作成する前に登録団体との協議を持つべきではなかったでしょうか?お答えください。また、このようにして助成金事業が廃止され、新事業である「すてっぷ市民協働フォーラム」が始まったわけですが、この新事業の概要、2023年度の参加人数、実施日数、予算額と市の評価をお答えください。加えてこの新事業がどのように地域の悩みなどの具体的課題解決に寄与しているのか、また困難女性支援のニーズに応じた包括的かつ継続的な「つながり続ける支援」をどのように推進しているのか、お答えください。また、財団が助成金事業の廃止を決定した後に、豊中市から登録団体への説明の中で助成金事業廃止の理由は「広がりがない」とされましたが、新事業はどのように広がりがあるのかについてお答えください。
豊中市:各種事業については、市民、事業者、団体等からさまざまなご意見を頂戴しており、その内容は指定管理者と情報共有しています。
フォーラムについては、昨年度は「女性の力で政治を変える」をテーマに公募の運営委員による8回の会議を経て、令和6年1月24日に開催、内容は若者世代の政治参画促進をめざす団体の代表者による基調講演と元議員・市民団体メンバーによるシンポジウムでした。参加人数は67人で、経費は講師への謝礼等567,755円を支出しました。
本事業について、市の年度評価で「多数の参加者があったことから、市民ニーズに沿った事業であったと考えられる」としております。女性が日常生活で抱えている問題や生きづらさの要因が政治分野をはじめとしたジェンダーギャップと密接に関わりがあることに気づき、行動変容につなげてもらう契機となったと考えています。
最後に新事業の広がりについてでありますが、助成金事業は主に特定の登録団体が対象でしたが、この事業は市民主体で企画運営にあたるとともに、地域で活動している方に登壇頂くなど、より多くの市民の協働と参画を得ることができたと考えています。
山田:まず持って、財団に廃止を促す文書「指定管理業務における助成を伴う事業の再編について」を作成する前に、登録団体との協議を持つべきではなかったか?との問いに全く答えていただいていません。市民との協働事業の廃止に関わる決定に当事者市民との協議を持つべきでした。
2022年度に廃止になった助成金事業の年間経費は新事業である「すてっぷ市民協働フォーラム」の585,495円とほぼ同額の567,755円でした。新事業についての市の評価は「多くの参加者があった」とのことでしたが、廃止になった助成金事業への参加者は466人で新事業の7倍ありました。実施日数はキャラメルの展示日数10日間を含め30日間です。内容も、6講座、そして6つのテーマでした。テーマについて具体的には女性の政治参画、シングルマザー問題、外国人親子が抱える教育問題、戦争における女性の著しい人権侵害、人権やジェンダーの視点から平和の大切さを考える、など多岐に渡り、実施状況を比べても誰の目にも明らかですが、廃止となった助成金事業の方がよほど広がりがあり予算の使い道として大きな意義があったと判断せざるをえません。多くの市民が不可解に思っています。
次に行きます。豊中市行政文書管理規則第21条に「意思決定を行うに当たっては文書を作成して行うこと並びに事務及び事業の実績については文書を作成することを原則とする」とあります。
豊中市は『文書「指定管理業務における助成を伴う事業の再編について」を作成するに至る意思決定が、人権政策課の事務所で、執務中の会話で行われたため、議事録を作成しなかった』としていました。市民と共同で進める事業廃止に関わる事項の決定プロセスにおいて、当事者にも見えない、市民にも見えない非常に不透明な行政活動が行われていると、言わざるを得ません。公文書管理法は、第1条において、公文書が「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であることに鑑み、「国民主権の理念」にのっとり、「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的」とし、第4条において、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」をも、検証することができるよう、文書を作成することを義務付けています。ここで想定されていることは、他者による事後検証を可能にするための記録の作成です。そのような記録が作成されてこそ、行政の恣意的運用を抑制することができ、将来の人々が過去を振り返ったとき、過去に学び、将来の行政に生かすことができるのです。参考事例として述べますが、今年度も残念ながら同じようなことが行われました。財団が、シングルマザーの相談会の広告画像をHPから取り下げることを決定した場所が「路上会議」であったとして、文書を作成しませんでした。一体どうなっているのでしょうか?やはり、この、市の市民との協働の施策を軽視する態度が、財団に影響を及ぼしているのではないでしょうか?要するに、市民活動への市の軽視が、財団の「路上会議」なるもの、いわゆる路上での「たちばなし」において、市民活動の協賛事業実施に影響を及ぼす決定を行い、会議録も作成しないという残念な姿勢を招いているのではないでしょうか?
2問目です。以上の点を鑑みて、事実上助成金事業廃止のきっかけとなるこの文書「指定管理業務における助成を伴う事業の再編について」の作成に至るプロセスで「執務中の会話で決めた」ことを理由に会議体を持たなかったことが結果として会議録が残らなないことになったと思うのですが、
そもそもこの「会議体」を持たなかったのは、逸脱行為または怠慢ではないでしょうか?市民と協働での取り組みに対する、市の姿勢について市の見解をお答えください。
豊中市:市として、助成金事業の現場、課題、今後の方向性について、共通認識を持った上で、指定管理者と話をしたものです。
市民との協働での取り組みに対する市の姿勢について、男女共同参画社会の実現には、市民、事業者、グループ・団体、関係期間等の皆様と連携、協働して取り組むことが不可欠と考えております。
山田:「共通認識があり、会議体を持たなかった」とのことですが、そのような弁明は到底通用しないと思われませんか?
財団の市民登録団体との協働事業の廃止などに関わる重要な決定について「執務中に口頭で決めた」や「路上会議だった」などを口実に文書を残さないと言うことが人権政策課そして財団の中で常習化していることが見受けられます。
3問目です。財団の業務執行理事が市の職員です。シングルマザー相談会の広告画像をHPからとり下げると路上会議で決定をしたのもこの職員だと聞いていますが、市の職員がどのような経緯で業務執行理事に就任したのか、お答えください。また、財団HPに業務執行理事の肩書で、職員が入っていたら、市民は市の職員が業務執行理事になっているんだと思いますよね?次年度指定管理の切り替えを控えて、利益相反とも受け取られかねないのではないでしょうか?副業規定への抵触もないのでしょうか?お答えください。
豊中市:市は財団の人事に関与していません。当該職員については、市内部を含めて適正な手続きを踏んで、当該財団の役員に就任しているものと認識しています。また、利益相反にあたらない、副業規定への抵触もないと考えております。
山田:傍聴されているみなさんいかがでしたか?問いに答えてもらっていませんよね。
市民活動を舐めているとしか思えない。
意見・要望です。
この質疑の冒頭箇所でわかるように、2022年に廃止となった助成金事業はテーマは多岐に渡り、一方、新しい事業はわずか一つのテーマです。参加人数も市民の参加も644人ありました。それに対し新事業はわずか70人です。
誰の目からみても助成金事業は豊中市、及び市民に寄与していたわけです。財団も中核を担う事業だと評価をしていたこの助成金事業、市が財団に廃止する方向性を伝えたタイミングはレイシストからのクレームがあった直後でした。
そして市に方向性を示された財団は、市民との協働で取り組んだ事業を市民になんの相談もなしに廃止にした、その廃止に関わる文書作成に至ったプロセスも不透明で会議記録そのものがないので、検証すらできない状態でした。これはどう考えても問題です。
そして、執務中に口頭で決めたことを理由に、会議体ではないからと文書は作成しないと言う市の市民活動への舐めた態度が、今年度の財団の姿勢、判断、すなわち、市民で構成される登録団体シングルマザーの会の相談会の広告をHPから削除する決断について「路上会議」だったので会議録作成しなかった、に関わっている、姿勢が伝染している、負の連鎖があるのではないでしょうか?
「執務中に口頭で決めた」、「路上会議だった」、市民をバカにしているとしか考えられません。
「路上会議」は財団の発言だったにせよ、市民協働部人権政策課は市民協働部と名乗る資格はないと思います。
ジェンダーギャップ指数がまだまだ低い日本では、男女共同参画を進めようとすると、必ず強いバックラッシュはおこります。これにいちいち屈していたら、男女共同参画社会は実現しません。そして男女共同参画社会の実現なしには、本質的な困難女性の課題解決は不可能です。市や財団にはレイシストやセクシスト、または男女共同参画推進をよく思わないようなクレイマーからの苦情には毅然とした対応を求めます。そして、市民との協働を大切にしていただく、対話を大切にしていただくことを切に願います。
ここ豊中市の人権を守る姿勢、取り組みは、かつて他市にさきがけた優れた歴史があったのではないでしょうか? 子どものころ、それこそ先進国にひけを取らない「人権の豊中」、と誇らしささえ覚えていました。
それが、今、市民協働部、人権政策課で民主主義の根幹が揺らいでいることが、この質疑をお聞きになった方、ご覧になった方に伝わったかと思います。
今後も注視してまいります。以上です。
質問をおわります。